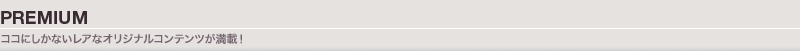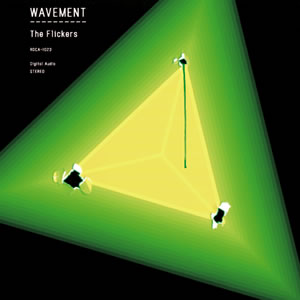<The Flickers 『WAVEMENT』 Interview>
──そもそもThe Flickersはいつ頃に始まったバンドなんですか?
安島:
2005年頃ですね。最初は遊びでやってる感じでした。そこから徐々にのめりこんでいく形で本気になっていって。
──当初から今みたいなエレクトロポップのスタイルだったんですか?
安島:
そうではないですね。ギターロックでした。でも、やりたかったことは今の音楽に近かったと思います。
──The Flickersのサウンドには80'sの感覚がすごくありますよね。それはどういうところから?
安島:
やっぱり、ポストパンクとかニューウェイヴと言われる80年代の音世界っていうのがすごく好きだったんで、自然にそういうところの音色を出そうとしてるんだと思います。ジョイ・ディヴィジョンとか、ニュー・オーダーもすごく好きでしたし、すごくシンパシーを感じたので。あとはストロークスとか、ヴェルヴェット・アンダーグラウンドとか、日本人でしたら、ブランキー(・ジェット・シティー)とかスーパーカーとかミッシェル(・ガン・エレファント)とかも好きでしたけど。
──皆さん、影響を受けた音楽は共通してる感じなんですか?
堀内:
そうですね、結構共通してると思います。
──でも、80年代はリアルタイムではないですよね? どういう経路から知って、どういうふうにハマってった感じだったんですか?
安島:
高校生の頃はパンクや激しい音楽が好きだったんですけど、そこからポストロックやエレクトロニカとか、エイフェックス・ツインのようなものを聴くようになっていって。そこからもう一度歌が聴きたいと思った時に、ニュー・オーダーやジョイ・ディヴィジョンのようなところに辿り着いたんです。時代的にも、70年代にパンクが盛り上がった後に、そこに敗北感を持って快楽的な音楽に流れていくっていうところにシンパシーを感じたというか。だから、メロディもポップなのに悲しさを感じさせたりするようなところがすごく好きで。
──The Flickersの曲の作り方って、ひとつのフレーズをループさせていくのがポイントですよね。同じビート、シンセや歌の言葉を繰り返して、なかでだんだんテンションが上がっていく。そういうところにすごく快感を覚えるみたいな。
本吉:Bメロからサビになって、サビでもリピートする感じは昔からありましたね。
安島:
クラブミュージックが好きだったのもあるし、あと言葉って、言えば言うほど意味が限定されていくと僕は思うんです。同じひとつの言葉をリフレインとして繰り返し言うというのは、そうじゃなくて、ただ感情のぶつける入れ物としてあるんじゃないかなって思います。言葉の体裁を持った感情のぶつけ場所っていうんですかね。「意味とか知らねえ!!」みたいな(笑)。
──まさに1曲目の「lovender」はまさにそういう曲ですよね。《終わらない今日は続きを歌うのさ》という一つのフレーズを歌ってるんだけれども、声と歌い方で、それがつぶやきにもなってるし、嘆きにもなってるし、逆ギレにもなってる(笑)。
一同:
(笑)。
安島:
前半ではクールでも、ちょっとずつ、「だんだんイライラしてきた!」っていう。一生懸命考えてても、「俺らはそんなスマートじゃねえや!」みたいな(笑)。そういうところに辿り着いたりします。やっぱり自分にはそういう部分が今必要な気がして、歌ううえで。
──2曲目の「vivian girls」はヘンリー・ダーガーの『非現実の王国で』にインスパイアされた曲ですよね。
安島:
そうです。
──あの人は、非常に孤独で、とてつもなく巨大な妄想を持っている人ですよね。そこに、ものすごくシンパシーを抱いているような曲。
安島:
そうですね。作品も大好きですし、彼の生き方にシンパシーを感じます。去年、ダーガーの絵を見て、すごく勇気づけられたんですよね。ちょうどデビュー前の時期で不安になっていたところもあったんですけど……人に嫌われたとしても、上手くいかなかったとしても、俺は、俺の信じることをやっていいんだって再確認できたというか。
──この「lovender」と「vivian girls」っていう曲から伝わってくるんですけれども。The Flickersはダンスミュージックだけれど、ただ騒いで楽しんでオッケーな音楽じゃないですよね。モヤモヤした孤独な精神性がその裏側に表れている。
安島:
僕はたぶん……悲しいから踊りたくなるとか、そんなところだと思いますね。イヤなことがあると、よく河原とか行って橋の下で音楽聴いて踊ったりする。見られたら恥ずかしいけど(笑)。苦しかったり、悲しかったり、辛かったりすることはやっぱりエネルギーになっていて、それでもやっぱり表現することは最終的にポジティヴなものでありたいといつも思うんですね。前を向くための何かでありたい、と。それを歌ったことによって自分も強くいられるとか、それを聴いてくれた人にとって何か力になるような、寄り添うようなものでもいいし、一緒になって怒れるものでもいいし、一緒に泣くようなものでもいいと思うし。ダンスミュージックっていうフォーマットは、そういう気持ちの表れだと思います。
──それこそニュー・オーダーの「ブルー・マンデー」なんて、そういう曲ですからね。出発点としては孤独があるかもしれないけれど、作り出そうとしてる光景には歓喜があるそういうのが結構理想像であったりするんじゃないですか?
安島:
そうですね。やっぱり聴いてもらう人には、踊ってほしいし、気持ち良くなってほしいですよね。僕らの音楽に触れる人にとって、とにかくポジティヴなものであれたらなとは思います。
──じゃあ、最後に。バンドとして5年後、10年後にはどういう存在になっていたいと思います?
安島:
まあまあのバンドでいいとは思ってないです。大きなバンドになりたいですね。あとは、やっぱり丸くもなりたくない。いつも自分たちを壊していく、驚かせていくようなバンドでありたいなと思いますし、革命的でありたいと思います。
本吉:同じ場所にいつづけるんじゃなくて、どんどん変化していけたらな、という。
堀内:
あとはやっぱり、僕らが高校生とか若い時とかに影響を受けたバンドと同じように、聴いた人の心に残るバンドになりたいと思いますね。