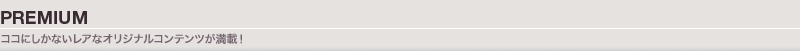関西を拠点に活動を続け、そのアグレッシヴなライヴ・パフォーマンスで注目を集めるスリーピース、ジラフポットが新たなEP『Last Man Standing』を2月11日(水)にリリースした。昨年、バンド初の全国流通盤『Hydro human』と精力的なライヴ活動で俄然注目度を高めた彼ら。新作は、獰猛なバンド・アンサンブルとリリカルなメロディ・ラインのセンスという、バンドのダイナミック・レンジともに、サウンドに漂う色気も盤に刻み込んでいる。3人に新作制作のプロセス、そして今後の展望について訊いた。メンバーの発言からも、3者の個性のケミストリーにより、ジラフポットのパワフルな音の固まりと強いリリシズムが生まれていることを感じていただけるだろう。
Interview & Text : Kenji Komai
Live Photo : Ohagi
Interview & Text : Kenji Komai
Live Photo : Ohagi
|
|
「Black designer」 Music Video
|
「スターチャイルド」Music Video
|
|
ジラフポット : Head Held High Tour
| |
|
DATE : 2015.2.27 (fri)
VENUE : Chiba LOOK, Chiba OPEN : 18:00 / START : 18:30 GUEST : tricot / フレデリック INFO : LOOK 043-225-8828 DATE : 2015.2.28 (sat) VENUE : Koriyama CLUB #9, Fukushima OPEN : 17:30 / START : 18:00 GUEST : tricot / フレデリック/ 夜の本気ダンス INFO : GIP 022-222-9999 DATE : 2015.3.1 (sun) VENUE : Sendai PARK SQUARE, Miyagi OPEN : 18:00 / START : 18:30 GUEST : SUPER BEAVER / ココロオークション INFO : GIP 022-222-9999 DATE : 2015.3.6 (fri) VENUE : Hiroshima NAMIKI JUNCTION, Hiroshima OPEN : 17:30 / START : 18:00 GUEST : コンテンポラリーな生活 / ユビキタス / 彼女 in the display / BUGZSTTACK(広島) INFO : セカンドシーン 082-212-0810 DATE : 2015.3.8 (sun) VENUE : Fukuoka QUEBLICK, Fukuoka OPEN : 17:30 / START : 18:00 GUEST : コンテンポラリーな生活 / ユビキタス / about a ROOM(福岡) INFO : BEA 092-712-4221 |
DATE : 2015.3.13 (fri)
VENUE : Nagoya CLUB UPSET, Aichi OPEN : 18:00 / START : 18:30 GUEST: avengers in sci-fi / コンテンポラリーな生活 / 空きっ腹に酒 INFO : サンデーフォーク 052-320-9100 -One Man Live- DATE : 2015.3.15 (sun) VENUE : Shimokitazawa SHELTER, Tokyo OPEN : 18:00 / START : 18:30 INFO : SHELTER 03-3466-7430 -One Man Live- DATE : 2015.3.22 (sun) VENUE : Osaka RUIDO, Osaka OPEN : 18:00 / START : 18:30 INFO : RUIDO 06-6252-8301 -Extra Show- DATE : 2015.3.31 (tue) VENUE : Kobe TAIYO-TO-TORA, Hyogo OPEN : 18:30 / START : 19:00 INFO : TAIYO-TO-TORA 078-231-5540 |
 |
ジラフポット Official Website
http://giraffepot.com/ |