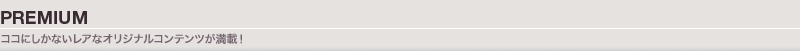<Nothing's Carved In Stone 『Silver Sun』 Interview>
──アルバムもリリースされ、ツアーもスタートしていますが、現在の手応えはいかがですか?
生形:
いまのところはすごく順調です。いままでにないくらいの感触、演奏もすごくまとまっているし、多少ミスもあるけれど、それも含めて、バンド内の空気もいいし。
村松:
いい感じでやれています。今までのツアーを通してオープンになってきている部分がさらに勢いづいてきた。いいかたちになっていると思います。
──ナッシングスはこれまでの3枚のアルバムでも、作品ごとに新しい表情を見せてくれました。ニュー・アルバムの『Silver Sun』は前作『echo』の緻密に構築されたプロダクションを経て、再びライヴのダイナミズムに回帰している印象があります。この1年で何か心境の変化はあったのでしょうか?
生形:
2011年は『echo』を出してツアーを回って、『echo』までは、バンドとしてはアルバムごとに幅を広げていったイメージがあるんです。もちろんロックがメインだけれど、ちょっとファンキーなのもできるし、違う方向もできる。『echo』は特に、いろんな振り幅の曲を詰め込んだアルバムで、3枚出してきて、幅を広げる方向性はある程度やりきった感があって。そこから今度はそぎ落とす作業を行なって、自分たちがほんとうに好きなものが何なのか分かったりするんですよね。今ナッシングスがやるべき音楽は何かというのが、自然に分かってきたんです。
だから「どういうアルバムを作ろう」とか4人で話したりもしなかったし、でも出てきたのはこういう曲で。すごいシンプルで、いらないものを全部そぎ落として、ビートとリズムとフックのあるメロディとがあるアルバムになったと思います。
──ナッシングスの幹の太さが伝わってくるというか。
生形:
それが核だと思っていて、それがしっかりしていないと、バンドは良くならない。
村松:
最初の印象は、もっと80年代やニューウェイヴの方に寄っていくと思っていて。エレクトロが好きで聴いていて、楽屋でも共有して「こういうのいいじゃん」と言ってる音楽もそういうのが多かったので。でもそこに行かずに、みんな持ってくるアイディアはロックなリフばかりだった(笑)。
──アルバムとしてのディスカッションはそんなになかったということですが、仕上がりはオルタナ感が色濃いですよね?
村松:
真一も言っていましたが、自然なかたちで、自分たちの好きな根本にあるところに帰ってきたんだろうなという感じはあります。ロックになってよかったと思っています。
──曲が揃ってみて、アルバムの全体像が分かった、と。
生形:
そうですね、普通だったらアルバムの全体をイメージして「メインの曲が早くできないかな」とか、「ちょっとしっとりしたのも加えよう」と考えるんだけれど、今回は何も考えずに曲を作っていって。だから、なんでこういうアルバムになったかと言われるとほんと難しいんですけれど、ただ4人が今エレクトロをすごく聴いていて、その要素もすごく入っていると思っていて。それは、人間のビートだけれど、ループの気持ちよさが、リフにしてもリズムにしても歌にしても影響されていると思うんです。
エレクトロという音楽とロックという音楽のどちらが新しいかといったら、新しいという意味では誰が見てもエレクトロ。だからってロックは古いものじゃない。一般的にロックって古いものに囚われがちなんですよね、それは俺が嫌いなんです。そこを変えたかった。生の音でここまで踊らせることとか、新しいことができるんだということを聞かせてあげたい。そういう意識はメンバー全員あったかもしれない。
──それは、具体的に打ち込みの音を取り入れるのではなく、それを生のグルーヴに活かすということですか?
生形:
ただ、うちら打ち込みも入っているんだけど、誰もがバンドの作品として聴いてくれると思っていることには自信がある。今回のアルバムでもそこはうまくできたと思っています。レコーディングについても、グルーヴは大事にしました。ビートの乗れる気持ちよさというか。
村松:
でも面白いよね。一発録りとかやってそうなノリなんですけれど、ベースとドラムは今回別々に録っているし。だから、単に勢いに任せずに、サードまでに構築したものを参考にして、もう一回一枚目を作った、みたいなことを俺たちのなかでは気づいたんです。でも、全部あと付けなんですけど(笑)。
──実際の制作のプロセスも今までと変わらなかったのですか?
生形:
曲の作り方は、弾き語りから作ったりすることもありますけど、基本は変わらないです。曲が揃ってみると、意外とビートのある曲が並んでいて。
──皆さんのなかで曲のアイディアが浮かんで具体化させるペースというのはどんどん早くなっているのでしょうか?
生形:
誰かが何かしらネタを持ってくれば、そこから広げられるので、困ったことはないです。アレンジに時間がかかるので、アルバムを作る前は、日数も限られているので怖いですけれどね。ただやってみるとできる。
──そこにはもちろん、ここまでの活動で得た4人のなかでの呼吸もあるのでしょうね。
生形:
あとは、みんなそれぞれいろんなところで活動しているので、それがいい作用をしていると最近思ったりします。いろんな刺激をもらって、ナッシングスで全部出す、みたいな。例えば今度ふたりでアコースティックでライヴをやるんですけれど、そういうこともバンドになったときに反映される。その刺激を反映させる場所は、俺にとってはナッシングスなので。曲作りに関しても、うちではうちのやり方でやっているのがいいのかなと思います。
──村松さんは、『Silver Sun』の制作で歌という部分で気持ちを新たにしたところはありますか?
村松:
今回はガラっと変えたというのではないんですけれど、もともとリアルなものを書くほうが好きなんです。ストーリーテラーになるつもりはなくて。それでも日記を書いているつもりもないんですけれど。根がネガティヴなので、下から見上げている景色が好きだったけれど、それでも書き方があるな、と気づいて。特にライヴを通して気づいた部分で、よくうちのバンドはライヴでも「コミュニケーション」と言うんですけれど、コミュニケーションをとって、バンド自身もツアーを通して変わっていく。それを肌で感じている部分があった。サード・アルバムのときに日本語詞でやることになって、オーディエンスとの言葉でとるコミュニケーションの大切さが身に染みたというか。そこにそれだけのエネルギーがあるから、当然相手がいたら、前向きな方向に動かしたいじゃないですか。そういうことができるようにならないとだめだなと思った。バンドで悲しいことを経験したこともあって、『Silver Sun』ではそうしたエネルギーを詰めることができた。歌詞についても、そうした気持ちで書いて、歌いました。
──言葉選びに関しても、今までであれば照れがあったような表現もできるようになったところもありますか?
村松:
ストップをかけていたところはきっとなくなったと思います。うまく表現する方法がわからないパーソナルな部分ってあったんです。ただ今回、「ファースト・アルバムを作った感覚」とさっき言いましたけれど、3枚作ってきたおかげで、バンドとのあり方というよりも俺自身がバンドになれたということがあるので。今までもそうだったんですけどね、実感としてというか、ヴォーカルとして貢献できるところがやっと分かってきたというか。
──村松さんの心の底から湧きでた言葉をそのまま出せばナッシングスになる、ということを再確認した、というようなことなんでしょうか?
村松:
そうじゃないとな、ということですね。
──例えば、バンドで曲作りを行なっていても、ギター一本で弾き語りしても歌えるかどうかが基準になる、というアーティストもいますが、ナッシングスの場合はそういうことは考えたりしますか。もっとメンバーの総体であったり、関係性のなかにバンドがある、という考え方ですか?
村松:
面白いのは、うちはどっちもちゃんと芯としてある。僕はあまりギター弾かなくてもいいんですけれど(笑)。歌の大切さというのは間違いなくあるし、そうじゃないと僕がいる意味がなくなってしまうので。歌を聴けば一枚通して聴ける魅力はあると思うし、楽器隊のことが好きで聴いている人は、楽器だけでハッとするポイントをかなり詰め込んでいるので楽しめる。
生形:
その人が言ってるのは曲の幹が何になるか、ということですよね。俺はすごく正直に言うと、弾き語りで歌えなくてもいいと思ってるんです。それは曲が、バンドでやって完成するものだから。それが弾き語りが素晴らしかったら弾き語りで出せばいいし。もちろん、真ん中にあるのは歌なんですけれど、うちのバンドが面白いのは、4人が集まると出せる音というところ。そうじゃないと、バンドでやってる意味がない。とはいいつつ、今度弾き語りをやるんですけど(笑)。もちろん弾き語りをやるからにはアレンジをしなおして、いいなと思ってもらいたいから。
──歌について質問したのは、メジャー第一弾のアルバムということで、これまで聴いたことのないリスナーにアピールしたいという意識はあったのかということが知りたかったからなんです。
村松:
オープンになった、と言いましたけれど、自分たちの音楽を聴いてほしいという気持ちはいつでもあるので、特に最近は思春期のバンドが持つような「俺たちかっこいいでしょ」みたいな勢いをすごく感じるし。もちろん新しい人にも聴いてほしいと思ってますけど、別にこれを作っている段階でメジャーの話が決まっていたわけではないんですよ。録り終わってからだから、もしかしたらモードは一致しているかもしれないですけれど、ほぼそこは関係ないです。
生形:
メジャーでの活動が始まってみて思うのは、昔から(メジャーを)毛嫌いしていたところがあって。正直に言うと、信用出来ない人がいるなという経験を何度かしたんです。バンドをずっとインディーズでやってきたんですけど、バンドがでかくなるとメジャーのバンドとやるようになって、自然とメジャーのレーベルのスタッフと接していくうちに、悪い人ばかりじゃないんだと分かったというか、むしろ適当な人は一部なんだと思って。活動しているうちに少しづつ開けてきた。逆に今回、メジャーから話が来て、うちのバンドがメジャーに行くって誰も思ってなかったと思うんです(一同笑)。それが面白いと思うし、自分たちにとって環境も変わるだろうし、すごいチャレンジになるだろうということは思いました。
──あえて環境を変えていくことは、当然これからのクリエイティヴの部分に変化を及ぼすでしょうか?
生形:
それもあると思う。『Silver Sun』が出たばかりで、制作として一緒にやったのは2ヵ月くらいだけれど、このジャケットにしてもすごくいろいろ考えて作ってくれた。これは俺らほとんど口出ししていなくて、スタッフが何回もやり直して提案してくれた。俺達は好きにやらせてもらってるし、とても心強くてよかったなと思っています。
──既に次のアイディアをかたちにしている作業に入っているのですか?
生形:
もう5、6曲はプリプロまで終わっているし……。
村松:
歌詞も2曲ぐらい書き終わってる。
──すごいペースですね。これからの展開はどんなものになりそうですか?
村松:
『Silver Sun』を作って、音の重なりとか、また真逆の方向に向かっていたりするので、メジャーでも一筋縄ではいかないバンドらしさを出し続けたいですよね。インディーズ好きの子とか、俺らがメジャーに行くことで遠くに感じてしまう子とか、メジャーに良くない印象を持ってる人っていっぱいいると思う。でもそう思わせてしまったら俺たちの責任なので。バンドを大きくしようという意思はあるし、最終的にはでかいスタジアムでもやろうと思ってる。だけど、今までと変わらぬスタンスで、俺たちバンドらしさのまま王道のロックをやり続けていけたらと思います。
生形:
俺らがメジャーに行ったから何かが変わるわけではなくて、むしろやることはまったく同じなんです。誰でも分かってると思うけど、メジャーに行ったから売れるわけではない。ほんとに変わらないんです。バンドをなんで始めたかといったら、曲を作ってライヴをやるために始めたのであって、俺らは常にそこだけやっていればいい。ツアーやって帰ってきて曲を作ってアルバムを作って、それを永久に繰り返していくだけだろうなと思います。